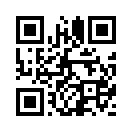2020年02月12日
PEラインを選ぶ上で知っておくべき2つのポイント
 多くの釣りにおいて、今や基本となっている“PEライン”ですが、皆さんはどのように選ばれていますか?
多くの釣りにおいて、今や基本となっている“PEライン”ですが、皆さんはどのように選ばれていますか?ラベルに印刷されている強力表示?それとも値段?ネットのインプレや人に勧められて?
以前からPEラインについては色々思うところがあり、色々試しながらも悩み続ける中で、幾らか知識も得てきたので、毎年フィッシングショーではラインを扱うメーカーに行って、色々と専門的な質問をぶつけることにしていました(笑)
ですが、毎年どこのブースで質問しても、一般的な回答ばかりで「私が本当に知りたい答え」を教えてくれる人には出会えなかったのですが、今年のフィッシングショーのダイワブースで、初めてラインに関する“本当のプロ”の方と出会うことができ、たくさんお話をお伺いすることが出来ました^^
その方は自分のメーカーのいいところだけを話すのではなく、PEラインそのものの基本的な知識や、ラインに対する考えなども交えながら、かなりの時間を割いて頂きました。
その中でたくさんヒントを頂き、私の中でモヤモヤしていたものがはっきりと表現できそうになったと思えたので、今回はPEラインを選ぶ時に「知っておくべき事」を、私なりに詳しく解説した記事を書きたいと思います。
※はじめに断っておきますが「PEラインの選び方」ではありませんのでご注意下さい(笑)
そもそも“PEライン”とは、“スーパー繊維”と呼ばれる素材のひとつである、“超高分子量ポリエチレン繊維”を使った釣り糸の事です。
“スペクトラ”や“ダイニーマ”という言葉を聞いた事がある方も多いと思いますが、それらは原糸に付けられた名称です。
ちなみに最近は“IZANAS(イザナス)”という名前を前面に押し出した商品がたくさんありますが、製造している東洋紡のページに書かれているように、そもそもダイニーマとイザナスは名称が違うだけで素材そのものは全く同じです。
そうなった経緯が気になる方は調べてみるといいと思いますが、今のほとんどの国産PEラインには東洋紡が製造しているイザナス(=ダイニーマ)が使われています。
(ちなみにシマノのパワープロはハネウェル社のスペクトラが使われています。)
イザナスの製品情報に書かれているように、イザナスには低グレードの“SK60”と、高グレードの“SK71”という2種類がラインナップされています。
素材特性としてSK71はSK60を上回っていますが、原糸そのものの値段は高くなってしまいます。
ちなみに以前のYGKのラインに表記されていた「スーパーダイニーマ」はSK60で、「ウルトラダイニーマ」はSK71の原糸を使っているということを表していました。
またダイワでは「スーパーPE」がSK60、「ハイパーPE」がSK71だったわけですが、0.6号200mのソルティガ8ブレイドを例にすると、2015年までのハイパーPEは定価13,000円だったのに、2016年にモデルチェンジされスーパーPEとなり定価4,400円と劇的に値下がりしています。(参考記事)
価格が大幅に値下がりしたのは“原糸のダウングレード”だけが理由ではなく、企業努力によるところも大きく、昔は「細いPE=高い」「太いPE=安い」というのがセオリーでしたが、今ではラインの太さと値段は関係なくなってきていることからもわかるように、技術革新の影響も大きいようです。
ちなみに、今ではSK71を使わなくても十分な性能のPEラインが作られるようになってきたという理由もあって、SK71が使われていると思われるラインは昔に比べると激減しています。
さて前置きはこれくらいにしておいて、いよいよ“本題”に入りましょう(笑)
PEを選ぶ上で知っておくべきポイント1
・パッケージに書かれた「〇〇lb」という表記にだまされない事
まず前提として、日本でPEラインを製造出来るのはわずか数社なので、各メーカーから発売されている日本製PEラインは、これらの会社の工場で作られているということを知っておいてください。
もちろんメーカー独自の仕様のものもありますが、「違うメーカーから出ているラインでも、中身は全く同じもの」も多く存在しているようです・・・
ここで、多くの釣具店で売られている「0.6号の8本撚りPE」のパッケージに書かれている表記を例として挙げてみますと・・・・
1.どこの釣具店でも見かけるA社の0.6号
「MAX 14.5lb 6.6kg」
2.ラインで有名なB社の0.6号
「最大強力14lb 6.4kg」「平均強力12lb(5.4kg)」「標準直径0.128mm」
3.ライン以外でも有名なC社の0.6号
「10lb 4.5kg MAX」「0.132mm」
3つのメーカーから出ているラインの値段がほぼ同じだとすれば、皆さんだったらどれを選びますか?
・・・聞くまでも無いと思いますが、パッケージだけを見れば普通1番を買うでしょう(笑)
だって“明らかに強そう”ですからね。
ですが・・・この3つメーカーから出ている0.6号の8ブレイドのラインは、メーカーで色々と調べた結果によると、“色が違うだけで、中身は全く同じモノ”だと結論付けられたPEラインだそうです。
「こんなことってアリ?」とも思えますが、ここに隠れている“カラクリ”が「MAX」とか「最大強力」といった表現です。
「MAX」とか「最大強力」とは、「一番強い部分はこれだけ耐えられます」と言う意味ですが、そもそもラインが切れるのは一番弱いところからですよね?
一番強い部分はこれだけ耐えらると言われても、強い部分は最後まで切れないので、それは全く意味の無い情報です。
つまり、何度も何度もテストを重ねて、たった1回だけ出た“奇跡の1回”の数字だったとしても、「MAX」や「最大強力」と表記してさえいれば、「ウソ」にはならないわけです。
でもそれって、IGFAクラスラインの表記を逆手にとったとしか思えませんが、本当にそれでいいのでしょうか?
少し解説しておくと、IGFAとは国際ゲームフィッシュ協会のことで、「〇〇lbラインでこんなデカいのを釣ったよ!」という記録の認定をしてくれるところです。
認定するにあたってラインの基準が曖昧では困るので、「〇〇lbの負荷で確実に切れるライン」を「IGFAクラスライン」とし、その基準に則ったラインで釣り上げた魚なら記録を認めましょうという話なのです。
IGFAクラスラインが日本で一般的に認知されたライン強力の表記とも思えませんし、ましてや記録認定のためのラインでも無いので、多くのアングラーを混乱させる原因にしかなっていないと思うんですよね。
それと比べると、B社の「平均強力」という表現は「だいたいその辺で切れる」という目安になるので、これは非常にありがたい情報です。
もっとも、バラつきが大きいのであれば役に立たない情報になってしまいますが・・・
仮にこの「平均強力5.4kg」が正しいとするならば、A社は平均から2割以上も高い数字をパッケージに大きく表記していることになります。
しかも、MAXだけはやたらと小さい字で書いているので、そこに悪意があるように感じてしまいますよね^^;
つまり、PEラインのパッケージに書かれた“MAX”や“最大強力”の数字の大小は、本当に知りたいラインの強さを表してはいないということなんです。
PEを選ぶ上で知っておくべきポイント2
・PEの性能は“編み密度”によって大きく変わるという事
 ここで同じ長さの中で編みこまれている回数(編み密度)の違いが分かりやすい“イメージ図”を作ってみました。
ここで同じ長さの中で編みこまれている回数(編み密度)の違いが分かりやすい“イメージ図”を作ってみました。どちらも同じ「0.6号、8ブレイド」で、同じ太さの原糸を編んだラインであっても、疎に編まれたPE(左)と密に編まれたPE(右)とでは、見た目から全く違っています。
当然のことながら性能も大きく変わってくるわけです。
PEラインの製造はマシンを使って原糸を編みこんでいきますが、疎に編んでいくという条件で100mのラインを作ると仮定しましょう。
ですが、もっと密に編んだ場合、同じ時間で75mしか作ることが出来ないとしたら、それだけ製造コストは上がってしまいます。
つまり、安くラインを作ろうと思えば、編み込みを甘くして疎編みのラインにしてやればいいのです。
付け加えて言うと、疎編みのラインでは、繊維が縦方向に揃っていることで新品時の直線強力は強く出るという性質もあるそうです。
つまり、パッケージに表記する“強力”の数字をより大きいものにすることができ、一見強いPEラインのように見せかけることができるわけです。
しかし疎に編んだラインは耐久性が低いので、強い直線強力が出るのは最初だけで、早い段階で落ちてきます。
また、編みこみが甘いと、糸と糸の間の“隙間”が大きくなるので、ラインが潰れて“きしめん”のようになりやすく、それだけ接地面積も大きくなり磨耗にも弱くなってしまいます。
さらに厄介なのは、サーフで使用していたケースで、波で巻き上げられた細かい珪砂(石英のカケラ)がこの“隙間”に入り込み、ラインそのものがヤスリのようになってしまうことで、ガイドが削られるというトラブルに繋がったことが実際にあるそうです・・・
 「じゃぁどのPEが密編みで、どのPEが疎編みなの?」というのは、メーカーでもなかなか公表していないところですが、ダイワの新しい“デュラセンサー”はかなり密編みになっているというお話をされていましたし、YGKのブースでは最高級PEラインの“オッズポート”の話を聞いた時も、芯があること以外に密編みになっているという話をされていました。
「じゃぁどのPEが密編みで、どのPEが疎編みなの?」というのは、メーカーでもなかなか公表していないところですが、ダイワの新しい“デュラセンサー”はかなり密編みになっているというお話をされていましたし、YGKのブースでは最高級PEラインの“オッズポート”の話を聞いた時も、芯があること以外に密編みになっているという話をされていました。色々と書いてみましたが、実際PEラインの良し悪しの評価は非常に難しいと思います。
MAX表示の問題も、「このラインは〇号なのに〇〇lbもあって、安くて強くてオススメです!」というインプレがネット上には溢れていますが、本当にそれでいいの?という思いがあったので、今回PEラインについて少し違った切り口で記事を書いてみました。
他にも、PEには表示号数と実際の太さがメーカーによって違うという大きな問題もありますが、それはまた別の機会にしましょう。
私達使う側の事をしっかり考えてくれるもメーカーがもっと増えればいいのになぁと切に願っております。
かなり長文になってしまいましたが、最後までこれを読んで頂きありがとうございます。
思うことを色々と書いてみましたが、「参考になった」と言って下さる方がいらっしゃれば大変嬉しく思います^^
フィッシングショー大阪レポート2020(目次)へ
Posted by T.A.K.U. at 13:17│Comments(2)
│タックル
この記事へのコメント
初めてコメントをさせていただきます。フィッシングショー後の記事が独自の着眼点で大変詳しくレポートされていますので、実は密かに毎年楽しく読ませていただいています。
今回のPEラインについてのお話は、とても勉強になりました。
4-5年前からPEラインの価格帯が急激に下がった印象を持っており、企業努力とは別に何か技術的な革新があったのか気になっていましたが、イザナスのグレードの違いや、スーパーダイニーマとウルトラダイニーマの違いはこれまで意識していませんでしたので、各社のPEラインを注意深く観察するようにしたいと思います。
一昔前の高価なPEラインばかりだと、どうしても価格で選んでしまいがちですが、現在はPEラインの価格が全般的に下がってきましたので、この記事で指摘されているように強度表記や編み密度のような異なる価値基準で選ぶのも大事ですね。
引き続きフィッシングショーネタの記事を楽しみにしています。
今回のPEラインについてのお話は、とても勉強になりました。
4-5年前からPEラインの価格帯が急激に下がった印象を持っており、企業努力とは別に何か技術的な革新があったのか気になっていましたが、イザナスのグレードの違いや、スーパーダイニーマとウルトラダイニーマの違いはこれまで意識していませんでしたので、各社のPEラインを注意深く観察するようにしたいと思います。
一昔前の高価なPEラインばかりだと、どうしても価格で選んでしまいがちですが、現在はPEラインの価格が全般的に下がってきましたので、この記事で指摘されているように強度表記や編み密度のような異なる価値基準で選ぶのも大事ですね。
引き続きフィッシングショーネタの記事を楽しみにしています。
Posted by shin1979 at 2020年02月13日 06:15
at 2020年02月13日 06:15
 at 2020年02月13日 06:15
at 2020年02月13日 06:15shin1979 さん
大変嬉しいお言葉をありがとうございます。
記事も楽しみにして頂いているようで良かったです^^
PEラインはどれも似たり寄ったりの見た目なので、何を基準に選ぶのかが難しいですが、魚と人間を繋ぐたった1本の線ですので妥協なく自分にとって納得できるものを選びたいと思っています。
今年はフィッシングショーのネタがたくさんあるので、力の続く限り頑張って書いていきますね(笑)
今後ともよろしくお願いします。
大変嬉しいお言葉をありがとうございます。
記事も楽しみにして頂いているようで良かったです^^
PEラインはどれも似たり寄ったりの見た目なので、何を基準に選ぶのかが難しいですが、魚と人間を繋ぐたった1本の線ですので妥協なく自分にとって納得できるものを選びたいと思っています。
今年はフィッシングショーのネタがたくさんあるので、力の続く限り頑張って書いていきますね(笑)
今後ともよろしくお願いします。
Posted by T.A.K.U. at 2020年02月13日 17:55
at 2020年02月13日 17:55
 at 2020年02月13日 17:55
at 2020年02月13日 17:55